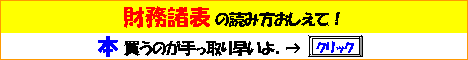|
クリスマスが待ち遠しくなる頃に出てくるのが,ユーミンのアルバム・・・もそうなんですが,毎度おなじみの自民党税制改正大綱.その中で,ここ数年,注目を浴びているものの一つが法人課税の実効税率引下げに関するものです.株式会社の場合,この引下げで最も恩恵を受けるのは株主です.
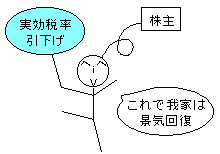
今年度(1998 年度)分の税制改正では,企業の純利益(税引後利益)を増大させて産業発展・景気拡大を促したい経済界(経団連など)・通産省と税収を減らしたくはない大蔵省との激しい綱引きがあったようです.その結果,ようやく 3.62%(= 49.98% → 46.36%)の実効税率引下げは実現しましたが,期待された割には「ウヒョー」と驚く程のものではありませんでした.それから 1 年,さすがに来年度(1999 年度)分の税制改正では,最近の激しい景気落込みに配慮して,5.49%(= 46.36% → 40.87%)の大幅な実効税率再引下げとなりました.
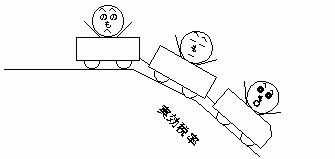
まあ,それはそれとして,この一連の引下げで直接的な恩恵を最も受けるはずの株主の声ですが・・・マスコミ経由ではほとんど聞こえてきません.という訳で,今回は,まず,法人課税の基礎知識を固めつつ,最後に,法人課税の実効税率引下げで株主がどの程度の恩恵を受けるのか考えてみましょう. まずは,「法人課税って何やねん!?」っちゅーとこから.まあ,株式会社が事業を営んで行く上で通常支払う税金というのは,思い付くだけでも,法人税・住民税・事業税・消費税・固定資産税・事業所税・印紙税・登録免許税・不動産取得税・有価証券取引税・自動車税・・・と切りが無いくらいです.が,実効税率ウンヌンということに関して扱うのは,法人税・住民税・事業税の 3 つです.そう,会社の所得に掛かってくる税金なのです.
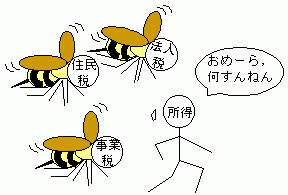
じゃあ,「この所得って何者やねん!?」となるのですが,コイツは,税法特有の言葉で,
と定義されまんねん.フフッ・・・また出てきちゃいましたね,税法特有の言葉が.この益金・損金という言葉がそうなんですが,これらは,それぞれ企業会計制度で言う収益(売上高・営業外収益・特別利益)や費用(売上原価・販売費及び一般管理費・営業外費用・特別損失)とだいたい同義です.なもんで,所得は税引前当期純利益(= 収益 − 費用)(→ 「各種利益の区別」)とだいたい同義なんですが,ところが何と!「事業税は,費用ではあるが損金には算入しない」とか「受取配当金は収益ではあるが益金には算入しない」とか・・・細かい(細かくない?)違いがチョコチョコあるので,所得はやっぱり所得としか言いようがおまへん.
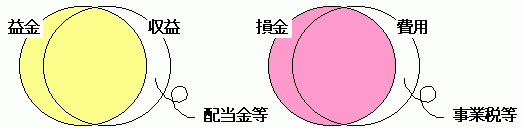
さてと,お次は実効税率.これは,「所得に対して掛かる税金の税率がおおよそ何 % になるのか?」という目安です.元々,法人税・住民税・事業税というのは,所得に対して何回か税率を掛けたりして計算するもので,上場してるような大きな会社の税率等は下表のようになります.
と,まあ,総て書き出すと上表のようになります.が,実効税率は,住民税の均等割や事業税の最高税率以外のもの(細字)を無視して計算します.下図は,来年度(1999 年度)の場合で,所得を 100 として順々に税額を計算して行って,最後に税額合計 40.87 を導き出し,実効税率 40.87% としています.ちとややこしいですねえ.まあ,そういう決まりですから・・・
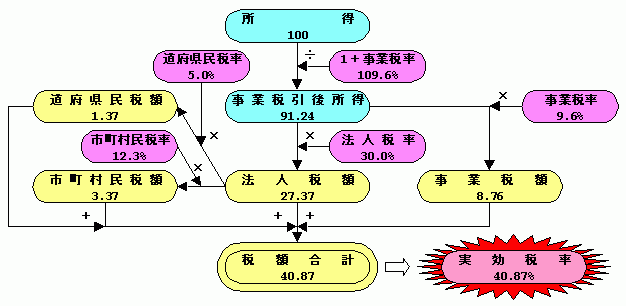
こうして,他の年度に関しても実効税率を計算すると,49.98%(1997 年度)→ 46.36%(1998 年度)→ 40.87%(1999 年度)という数字が出てくるのです.ふぅ〜,長い道程でしたあ. さてと,次はいよいよ株主の受ける恩恵ですが,収益から費用(∋ 事業税)・法人税及び住民税を差し引いた後の利益は株主のものでした(→ 「株式投資入門第 2 話:株主の権利 〜 出資側から見たメリット 〜」).ということは,収益と事業税を除く費用とが同じであれば,実効税率が低ければ低いほど,より多くの利益が株主の手元に残ることになります.実効税率が約 49.98%(1997 年度)→ 40.87%(1999 年度)と減ったということは,「株主の取分である当期純利益(当期利益)がおよそ 1.2(=(100.00% - 40.87%)/ (100.00% - 49.98%))倍に増える」ということです.となると,ということはですよ,「1 株当り収益還元価値もおよそ 1.2 倍に増える」(→ 「株式投資入門第 4 話:株式の市場価格と投資価値」)ということにもなるじゃないですかあ.おいしいでしょう.おっと,ヨダレが・・・
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||